口から食べて、その後は
口に入れたら、どうすればよかったのかな。
しっかり噛むのが大切だったよね。具体的には30回噛めっていわれてる。

たくさん噛むと何が良かった?
噛めば噛むほど賢くなれるかもしれないんだよね。

口を動かすことによる脳の刺激もあるけれど、何よりもまず噛むことの意味は、食べたものを細かくすることなんだよ。カホちゃんはみかんが好きでしょう、だからといって皮をむいたみかんを丸ごと飲み込んだりしないよね?
当たり前じゃない、そんなことしたら、のどを詰めちゃうよ。
大切なのは噛んで小さくすることと、唾液、要するに「つば」を出すことだ。唾液には消化酵素アミラーゼが含まれていて、食べものに含まれているでんぷんと反応して麦芽糖へと分解する。唾液は大人だと1日に1リットルから1.5リットルぐらい出ている。大事なキーワードとして「分解」を覚えておこう。
分解して細かくするから細いのどを通り抜けられる。唾液には、食べたものを体の中の下の方へ押し流してくれる役割もあるって教わったよ。
そうして食べものが胃に到着すると、そのシグナルを胃の中のG細胞が察知する。するとG細胞はガストリンを血管に分泌し、ガストリンが胃酸分泌細胞やペプシン分泌細胞などが集まっている胃腺に働く。その結果、胃の中に胃酸と呼ばれる塩酸とペプシンが分泌される。ペプシンは、たんぱく質を分解するんだ。

https://www.libroscience.com/pdf/cbt_4_sample.pdf

少し正確にいうとね、食べものを口に入れる前に嗅覚からのシグナルが脳に送られて、さらに口に入れた段階で味覚からのシグナルが脳に送られるの。それらのシグナルを受けて迷走神経が刺激され、塩酸とペプシノーゲンからなる胃液が分泌されるってわけ。
ちょっと待って! 塩酸って理科の実験で使ったことがあるけれど、先生が「取り扱いには注意するように、手に触れるとやけどするから」っていってたよ。そんな危険なものが胃の中に出てきたら、胃袋がやけどしちゃうんじゃないの。
ところが人の体はよくできていてね、ペプシンや胃酸が食べたものを分解すると同時に、ちゃんと胃酸から胃を守る仕組みがあるんだよ。だから、みんな元気でいられるんだ。
胃酸から胃を守る仕組みを、動物は進化のどの段階で持つようになったのだろうか?
胃から小腸へ、吸収の旅は続く
では、胃の次はどこになるのかな。
その前にちょっと教えてほしいんだけど、食べたものって胃では吸収されないの?
そう、胃は細かくするだけで、吸収するのは小腸だ。
さっきの胃酸の問題については、十二指腸で胃酸が中和されるから基本的に問題はないんだよ。
十二指腸の内表面にある細胞が、胃酸をシグナルとして感知するとホルモンを出す。ほかにも胃で分解されたたんぱく質や脂質をシグナルとして受け取る細胞が、別のホルモンを出す。そうやって消化が進められていく。要するにどんどん細かくなっていく。

その先が小腸ね。食べものたちには、長旅ご苦労さんってところかな。小腸にたどり着いた段階で、でんぷんはマルトースになっているの。たんぱく質は、アミノ酸が3~8個ぐらいつながったオリゴペプチドになってる。
それを小腸が吸収するの?

それがまだなんだよね。マルトースの大きさだと、小腸は吸収できないの。だからマルトースは小腸の表面にある微繊毛でグルコースに分解され、オリゴペプチドはばらばらにされてアミノ酸にまで分解されるのよ。
ということは、例えばお肉を食べても、徹底的に細かくされちゃうわけね。一体、どれぐらいの大きさなのかな。
アミノ酸はだいたい0.8ナノメートル、だから0.0000008ミリだな。
想像もできないな。

前に細胞の大きさが直径20マイクロメートルぐらいだって教えてあげたでしょう。20マイクロメートルは0.02ミリだから、アミノ酸は細胞よりもまだずいぶんと小さいのがわかるよね。そこまで細かくしてあるから、グルコースやアミノ酸は小腸の毛細血管に開いている穴から吸い込まれて全身に運ばれるの。ただ脂質はグルコースなどより少し大きくて、その穴には入らない。だから脂質はリンパ管の細胞の隙間から、リンパ管の中に入って全身に運ばれるの。
人の血管のうちの97%から99%ぐらいが毛細血管なんだ。これをつなぎ合わせると地球2周分ぐらいにもなるんだよ。
ばらばらにされた食べものは全身の細胞へ

全身に運ばれるということは、全身の細胞に届けられるということだよ。そして細胞のなかで起こる化学反応を代謝というの。
それって「息する編」で教えてくれた。ミトコンドリアの中で起こるいろいろな反応のことでしょう。

よく覚えていたね。ざっとおさらいしておくと、グルコースがピルビン酸になり、ピルビン酸が化学反応によってさまざまな分子になるわけ。そして最終的にはアデノシン二リン酸(ADP)からエネルギー通貨とも呼ばれるアデノシン三リン酸(ATP)がつくられる。このATPが体が必要とするさまざまなエネルギーの元になるんだよ。
つまりグルコースは代謝を引き起こすシグナルとも考えられるわけだ。
そこで少し疑問に思うことがあるんだけれどね。よく脳のエネルギー源はブドウ糖、つまりグルコースといわれるでしょう。それって本当かと思わずにはいられないんだ。例えば肉食動物は、そんなに糖分はとっていない。だからといって彼らの脳が動いていない、なんてことはないわけでしょう。だからグルコースをとらなくても脳はきちんと動くんじゃないかな。
グルコース以外にも脳のエネルギー源はありうるということか。
グルコースを取らなくても、脳はしっかりと機能する。その代表例がケトン食、糖質を控えめにして脂肪を増やす食事だね。

ケトン食ダイエットって炭水化物を少なくして、タンパク質と脂質をたくさんとるダイエットですね。私、やったことありますよ。
ケトジェニックダイエットをすると血糖値が安定して、自制心を高める効果もあるといわれている。
食べものって難しいね。
何が体外に排出されているのか
あとは食べた後に何が起こるのか。小腸の中で細かくされるといっても、食べたものが全部吸収されるわけじゃないでしょう。吸収されなかったものは大腸に運ばれるのね。

とはいっても大腸には小腸のように、何かを吸収するような組織はほとんど存在しないの。大腸の中を見ると、かなりなめらかな表面をしているよ。
ということは、大腸の中で食べものは吸収されないということ?

基本的にはね。大腸で吸収されるのは、ほとんど水分とミネラルだけね。
その代わり、大腸にはとても重要な役割がある。腸内細菌のことは覚えているだろう?
1000種類以上で合計100兆個だったよね。人間の細胞の数が37兆個だから、細胞の数よりもずっとたくさんの腸内細菌が、人の体の中で暮らしているわけでしょう。
その腸内細菌たちは、小腸で吸収されなかった不要物をエサにして生きているんだ。エサにするというのが、どういう意味かわかるよね?
細胞の中で起こる化学反応と同じ、化学物質を取り込んで反応、正確にいえば代謝をするんでしょう。

例えば食物繊維を細かく切って腸内細菌が取り込んでくれるの。つまり食物繊維をたくさん食べなさいというのは、腸内細菌くんたちを元気にしておこうという話でもあるわけ。それが最終的にはウンチになってでてくるわけだけれど、ウンチの3割ぐらいは腸内細菌だといわれている。
だからウンチを観察すると、腸内細菌の様子、そして大腸の中の様子などもわかるっていうわけか。最後に1つ疑問があるんだけれど「お腹が空く」っていうでしょう。このお腹は、胃のことなの、それとも小腸なの?
胃が空っぽになると、胃腺でつくられるホルモンのグレリンが脳にシグナルとして伝えられる。すると脳は「空腹」を感じるんだ。

脳にシグナルを送るといえば、実は小腸にはニューロンが1億個、脊髄と同じぐらいありますよね。
だから腸はセカンドブレインとも呼ばれている。ただし、腸は脳のコントロールを受けない。けれども、腸は脳をコントロールできる。腸はなかなか不思議な臓器だよ。
用語集
ガストリン
胃幽門部の粘膜や十二指腸粘膜に散在するG細胞から分泌されるアミノ酸17個のペプチドホルモン。
ペプシン
胃で働くタンパク質分解酵素の1つ。
迷走神経
12対ある脳神経の1つ。脳神経中最大の分布領域を持ち、主として副交感神経繊維からなるが、交感神経とも拮抗し、声帯、心臓、胃腸、消化腺の運動、分泌を支配する。
マルトース
麦芽糖とも呼ばれる、グルコース2分子がα-1,4-グリコシド結合した還元性のある二糖類。デンプンの直鎖部分に相当する。
グルコース
グルコース
ブドウ糖とも呼ばれ、分子式 C6H12O6を持つ単純な糖である。
ケトジェニックダイエット
人間のエネルギー源である三大栄養素(糖質・タンパク質・脂質)のなかでも、糖質の比率を下げていくダイエット方法のこと。摂取する糖質の量が減れば、体脂肪の分解が促され、肝臓で「ケトン体」と呼ばれる物質が作られる。この「ケトン体」をエネルギー源として利用する。
グレリン
胃から産生されるペプチドホルモン。視床下部に働いて食欲を増進させ、下垂体に働き成長ホルモン (GH) 分泌を促進する。


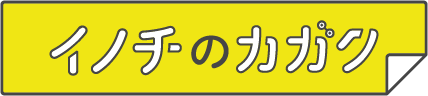

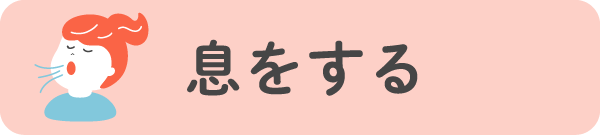
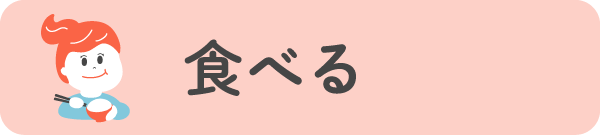

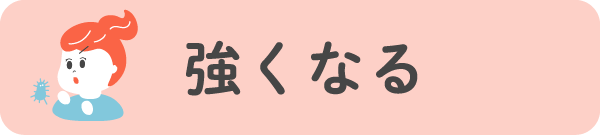
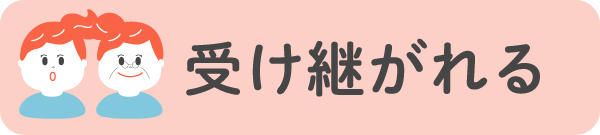
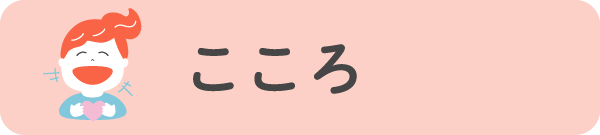

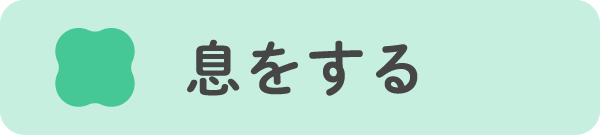
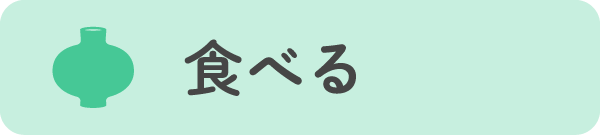
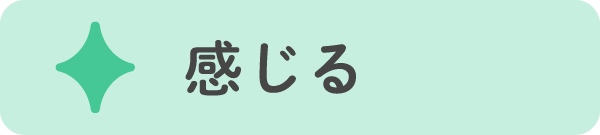
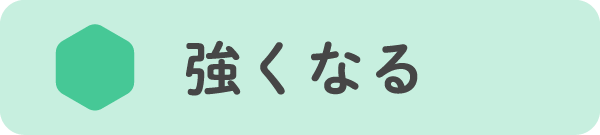
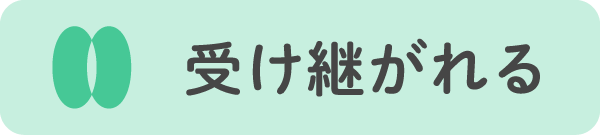
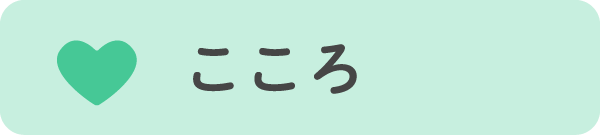

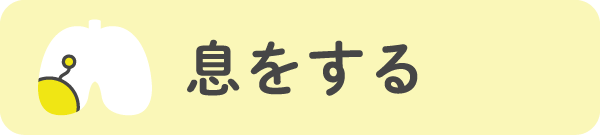
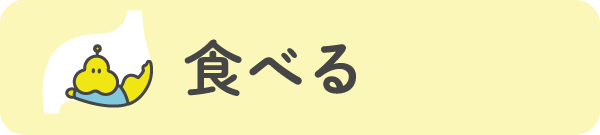
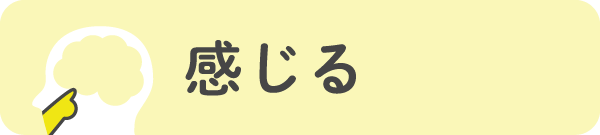
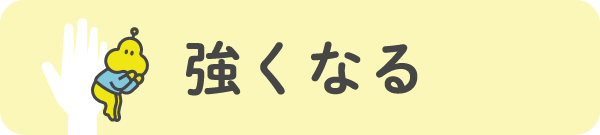
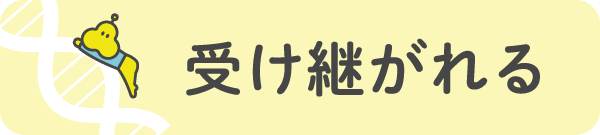
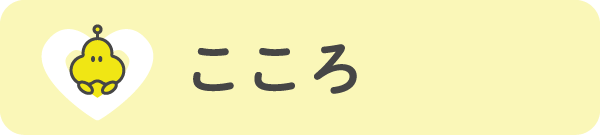


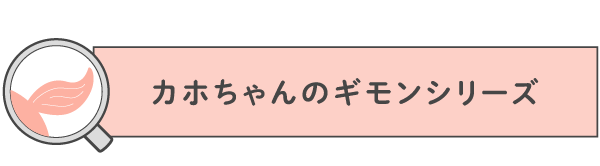


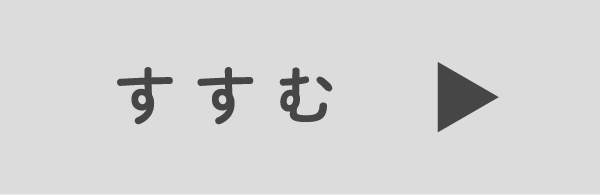






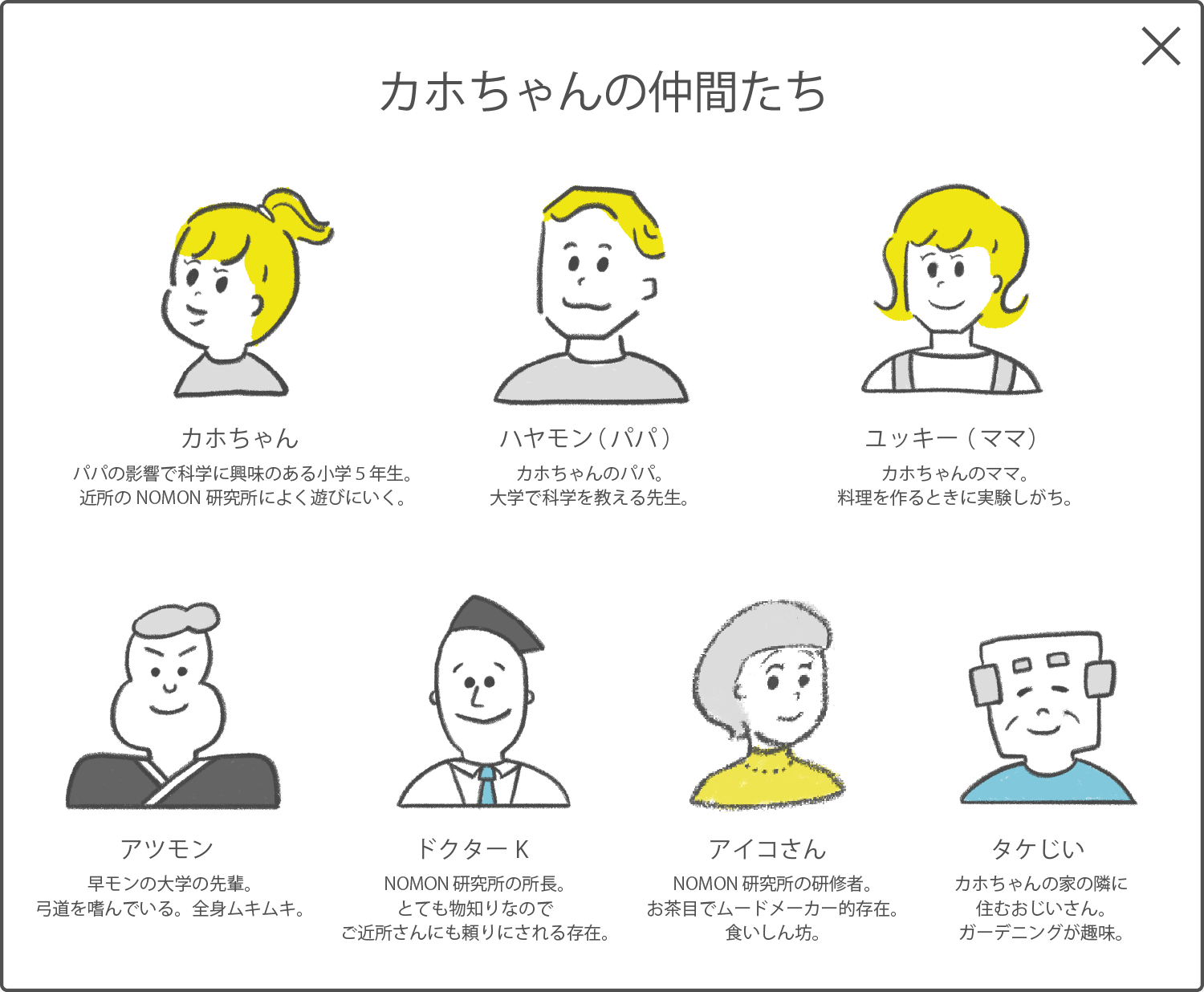
食べものって、当たり前だけれど口から体の中に入っていくでしょう。そしてのどを通って、次は胃に行ってという流れはわかるんだけれど、その間にどうなっていくのか、もう少し詳しく知りたいな。